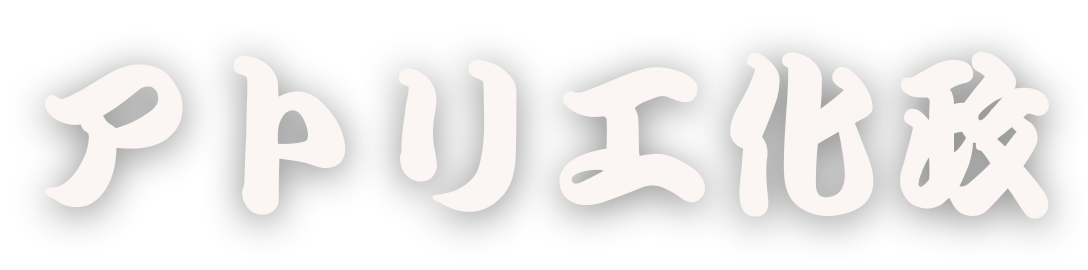※この考察は、NHK大河ドラマべらぼうのネタバレを含みます。
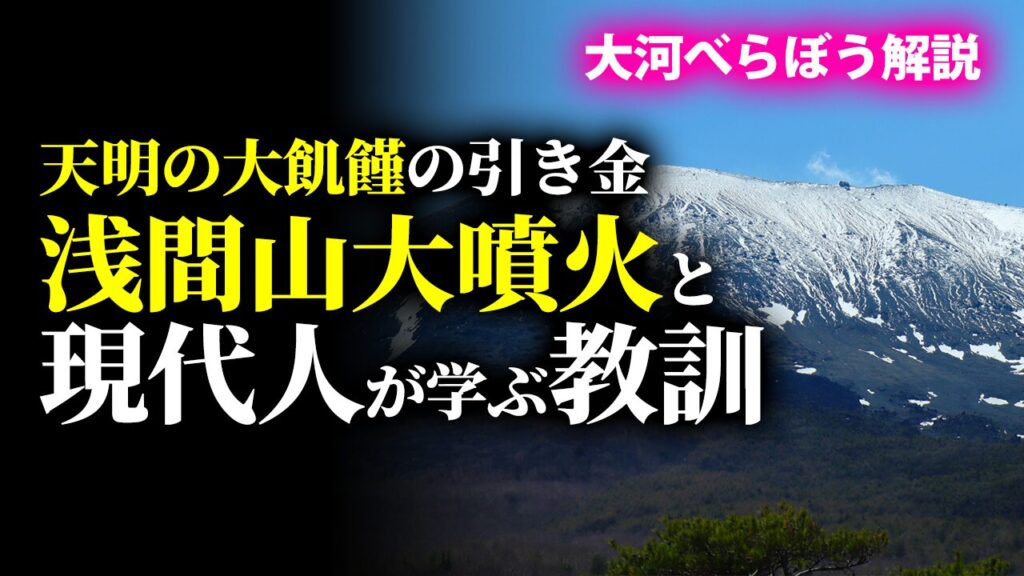
大河べらぼう第25話では浅間山の大噴火による混乱が描かれました。
 ほくさいぬ
ほくさいぬ最近は富士山噴火も注目されているから非常に興味深い内容だったぞ!
今回は、天明の大飢饉の引き金となった浅間山大噴火と現代人が学ぶ教訓について詳しく解説していきたいと思います。
⇩ちなみに、他にも大河ドラマべらぼうに関する記事を書いていますので、興味のある方はぜひ読んでいただけると嬉しいです!⇩
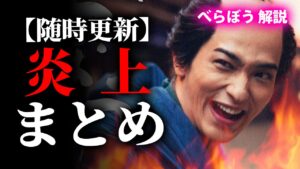
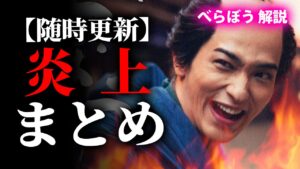
Q.天明の浅間山大噴火とは?
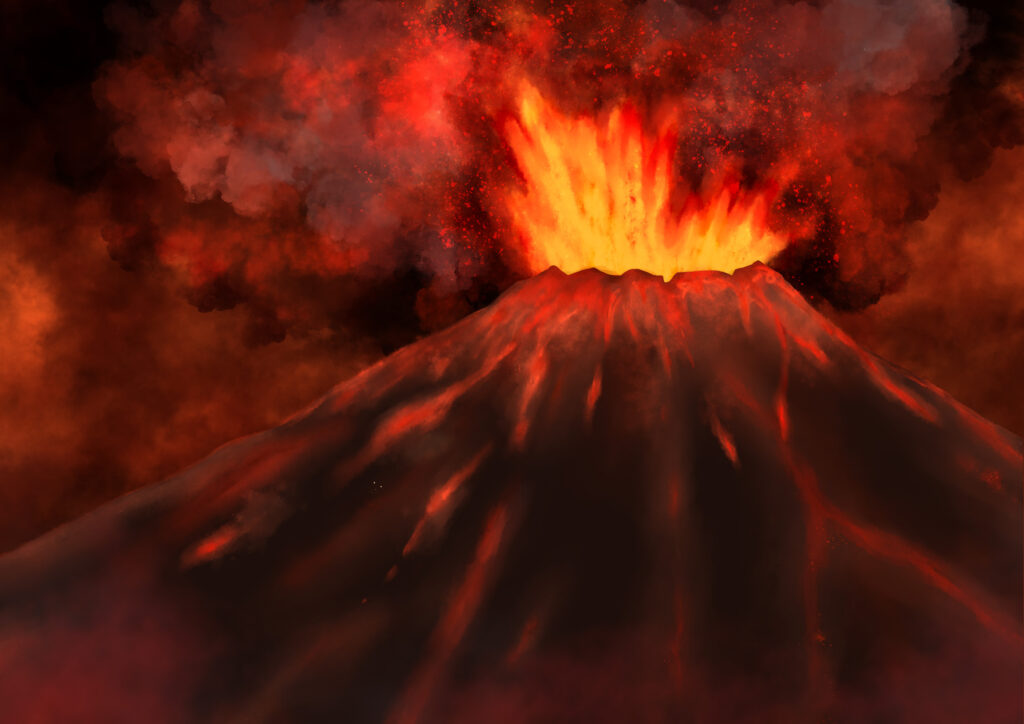
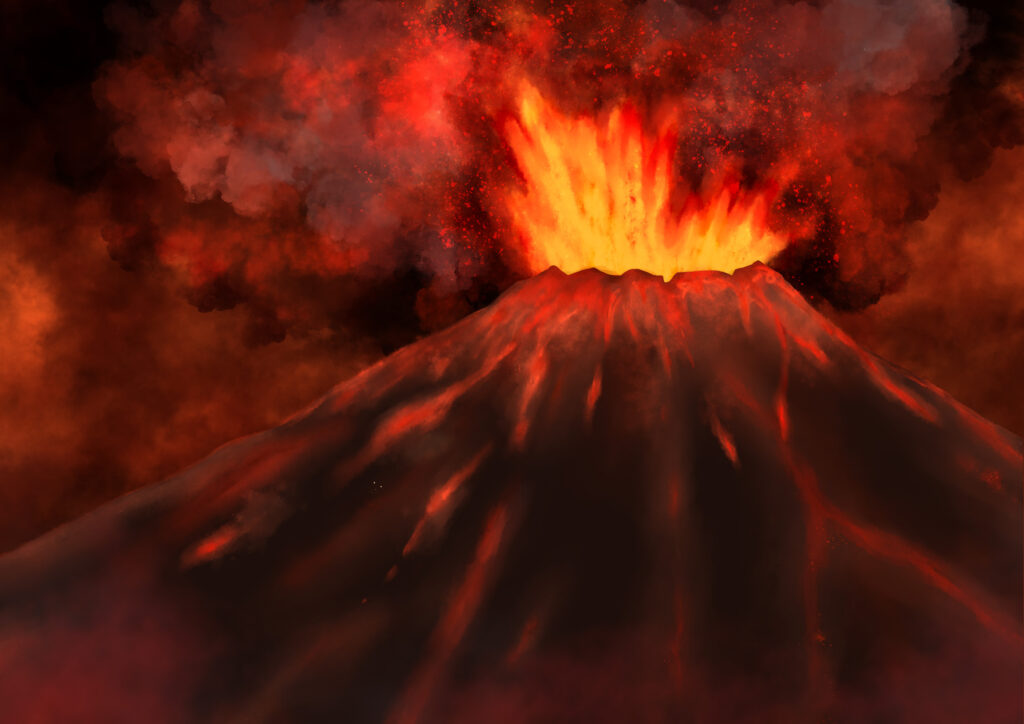
A,1783年に起きた江戸時代最大級の火山災害です。
天明3年(1783年)5月から小規模な噴火が始まり、7月7日〜8月5日ごろに最大規模の本噴火があったとされています。



噴火っていきなりバーンと来るわけじゃないのね



最近は世界的にも噴火のニュースが多いから、引き続き要注意じゃな
場所は、現在の群馬県・長野県の県境にある浅間山(標高2,568m)で、マグマ噴火と水蒸気爆発の複合型噴火が起きました。
大規模な火砕流と泥流(ラハール)が発生し、その灰は140㎞(直線距離)も離れた江戸の日本橋にも降りました。
その灰の量は驚愕で、約 1億トンの火山灰と軽石が放出されたと推定されており、それらは、吾妻川から利根川へと流れ込み、関東平野広域に洪水を引き起こしました。



噴火は灰だけでなく、洪水も引き起こすのね…
Q,被害の概要は?
A,推定1500人以上の死者を出し、村ごと壊滅してしまった地域もありました。
死者は推定約1,500人以上と言われ、数千軒の家屋が焼失・埋没、そして浅間山周辺の村(現在の群馬県嬬恋村・鎌原村あたり)は丸ごと壊滅してしまったと言われています。
鎌原村の悲劇(代表的被災地)
火砕流や土石流(天明泥流)によって、村人570人中477人が死亡しました。
村人93人は「鎌原観音堂」への避難し、奇跡の生存記録として今もなお語り継がれています。
異世界転生ギャグわんこ漫画
ほくさいぬ
最新話は2025年9月12日 更新!


Amazonで無料配信中!
Q,社会的影響はあったの?
A,はい。経済に多大なる影響を与え、天明の大飢饉を引き起こしました。
降灰による日照不足で作物が育成できなくなり、全国規模の飢饉へ繋がりました。
天明の大飢饉の死者数は全国で数十万人とも言われ、餓死、疫病、村の離散、親が子を売る「身売り」などの悲劇が広がりました。
一揆や打ちこわし(都市暴動)も頻発し、幕府の威信は崩壊していきました。



劇中で渡辺謙が演じている田沼意次が失脚する決め手になったのは、天明の大飢饉だよ。


当時はまだ科学の発展が乏しく、この噴火や飢饉をに対して多くの人々は「天変地異は神仏の怒り」と認識し、祈祷や修験道が活性化しました。
この出来事が「天明期の改革」や後の思想にも影響を与えていきました。
現代人が学ぶべき教訓はありますか?


噴火災害は、噴火単体の影響だけでなく複合リスクを意識すべきです。
噴火は、マグマや灰の影響ばかりが注目されがちですが、その後に起きる作物の不作や、社会不安からくる暴動など…複合的なリスクを意識しておくことが大切です。
今日の日本も、地震+火山噴火+作物不作+経済不安が複合的に襲う可能性は十分にありますので、それらを踏まえて対策しておくことが重要でしょう。
現代では防災マップで、地形・土石流のルート・火山灰の範囲などの知識は簡単に取得できますが、反面、暴動のリスクなどはなかなかイメージしずらい傾向があると思いますので、いざという時には、暴動が起きるエリアから脱出・もしくはできるだけ外出しなくてすむような環境を整備しておくといいかもしれませんね。
まとめ
天明の浅間山大噴火は、単なる自然災害ではなく、社会・政治・思想すべてに影響を与えた国難級の出来事でした。
現代の防災や政治のあり方を考える上でも、極めて重要な歴史的教訓を含んでいます。
大河ドラマべらぼうでは、それらをコミカルに学ぶことができるので、よかったらぜひ一緒に楽しみましょう!
気になる方は公式SNSもチェックしてみてください!
本サイトでは、アフィリエイト広告を利用、またはプロモーション記事が含まれている場合があります