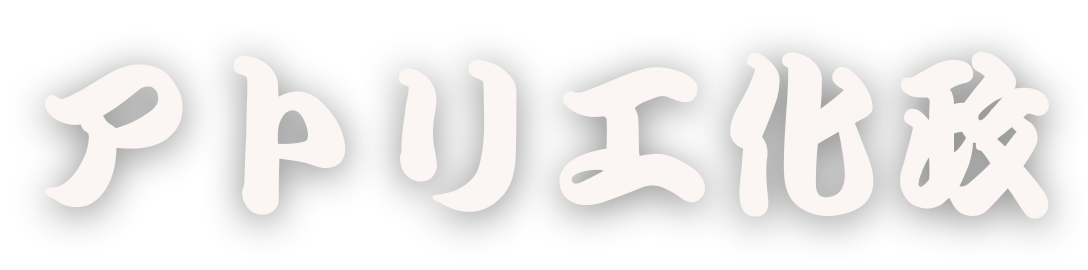※この考察は、NHK大河ドラマべらぼうのネタバレを含みます。
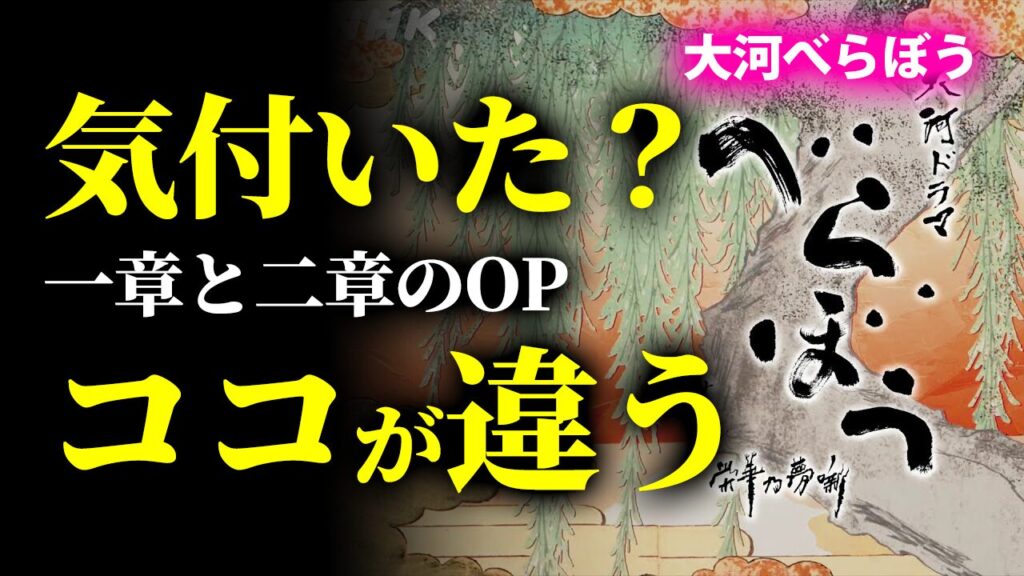
 おーいぬ
おーいぬついに第二章が始まったわね!



みんなはOPが微妙に変わったことに気づいたかな?
今回は、第一章と第二章のOPの変更点を徹底的に調査していこうと思います!
⇩ちなみに、他にも大河ドラマべらぼうに関する記事を書いていますので、興味のある方はぜひ読んでいただけると嬉しいです⇩
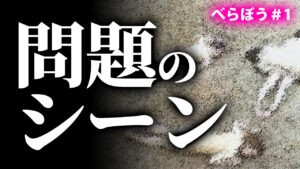
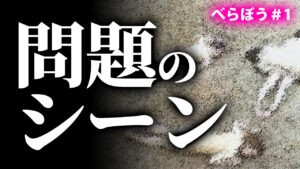
【00:09~】タイトルバックの色が違う
第一章では、物語の始まりを感じる朝焼けのような朱色でした。
第二章では、清々しいブルーに変わりましたよね。
蔦重の仕事が順調に大きくなり、「開店時間だよ〜」と声が聞こえてきそうな爽やかさがあります。
まさに耕書堂の歴史を表しているような演出ですね。



わしは蔦重のビジネスにおける青春期を感じたぞ。
【00:39~】本づくりの制作工程が違う
第一章では絵巻のようにつながった書物にさまざまな職人が加わっている印象を受けました。
どちらかというと、書物>制作に関わった人たち といった感じです。
第二章ではそれぞれの職人の顔が見えたり、本の制作が細分化されているような表現になっていて、今後はキーパーソンとなる絵師や彫り師、刷り師などが登場するのではないかと感じました!
第一章のイメージとは逆転して、制作に関わった人たち>書物 のような印象になりました。
さらに、出版した本のラインナップも増え、耕書堂がお客さんで賑わっている様子も表現されていて、とてもワクワクしてきました!
異世界転生ギャグわんこ漫画
ほくさいぬ
最新話は2025年9月12日 更新!


Amazonで無料配信中!
【01:14~】蔦重が歯車に追加される
第一章では、江戸時代の大橋を想起させるデザインの歯車の上を人々が歩く姿が映ります。
そこに追加される蔦重の姿。
まるで蔦重が江戸の街を動かす重要な一部となることを暗示しているかのようです。
【01:26~】幕府内の部下が がしゃどくろ になっていく。
田沼意次であろう人物の手前側に座っていた部下たちの顔が、北斎の描いた がしゃどくろ になっていくシーン。
第一章では、徳川幕府の次期将軍予定だった西の丸様が急逝(暗殺)。
老中の松平武元も死去(暗殺)。
さらに幕府の闇に気付いた平賀源内までも殺人の罪(冤罪)で獄中死…。
田沼の周りで不審死が相次いでいるのを暗喩しているのでしょうか…。
たった2〜3秒のシーンですが、不穏な空気を感じさせるシーンです。
【01:59~】赤富士に雷鳴がとどろく


葛飾北斎を代表する作品の一つである、富嶽三十六景「凱風快晴」が映るシーン。
第一章では美しい晴れの日でしたが、第二章では雷鳴とどろく大雨になっています。
蔦重の人生が一筋縄ではいかないと言うことを暗示しているのでしょうか。



ちなみにこの絵を描いたのはワシが70歳を過ぎてからのこと。
実はこのとき、すでに一代目蔦重は亡くなっているんだ。



蔦重は二代目がいたの?!



いたよ。
あまり詳しいことは残っていないが…。
ちなみに北斎に関わった版元たち(プロデューサー)について詳しく知りたい方は下の記事を読んでくれると嬉しいぞ!
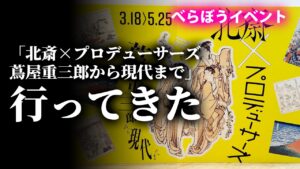
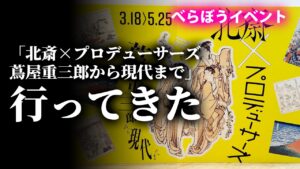
異世界転生ギャグわんこ漫画
ほくさいぬ
最新話は2025年9月12日 更新!


Amazonで無料配信中!
【02:16~】貝殻から黄表紙(漫画の原型)に変更
第一章で女郎たちのまわりを回るのは貝殻でした。
第二章では金色にも見えるような輝く黄表紙に変わっています。
黄表紙とは、言葉通り黄色い表紙がトレードマークの本。
最大の特徴は、笑える&風刺たっぷりの挿絵と文章が組み合わさったまさに現代の漫画の原型でした。
女郎たちの周りを回っていると言うことは、この本が女郎たちの知識・教養を育むツールとなっていたことを表しているようですね。
ちなみに第一章はなぜ貝だったのでしょうか。
それは絵が、喜多川歌麿の『潮干の苞 貝覆い』だったからです。



江戸時代の出版物については、以下の記事を読むとわかるわよ!
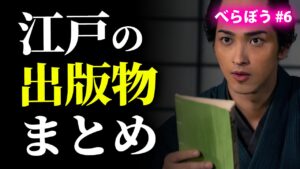
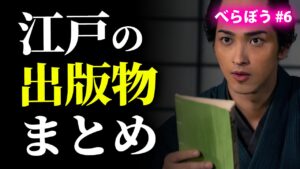
【02:23~】蔦重の持つ本が黄表紙に変更
第一章では、蔦重が初めて作った本である吉原ガイドブック「吉原細見」でした。
第二章では黄表紙になっていますね。
蔦重が黄表紙をメジャー本にさせるという暗示でしょうか。
本の表紙にはどうやら猫が描かれているようですが、詳しくはまだわかりませんので今後のストーリーに注目です!
【ラスト】蔦重の目の前に江戸の街が加わる
第一章では、貸本を背負った蔦重が、葛飾北斎の描く赤富士を眺めているシーンでした。
第二章では、赤富士の手前に江戸の街が追加され、さらに蔦重の後ろには江戸の人々も追加されています。
蔦重のビジネスヴィジョンが明確になり、江戸の街をターゲットとしたといった感じが出ています。
蔦重の後ろにいる人々は、蔦重に仲間が増えたのかのような印象に見えました。
【まとめ】
いかがでしたか?
第二章では不穏な雰囲気のシーンも追加されて、ますます目が離せなくなってきましたね!
個人的には幕府パートの部下ががしゃどくろになっていく部分が、物語をどう暗喩しているのかが気になります。



陰謀論好きなら気になるはず!
気になる方は公式SNSもチェックしてみてください!
今後も、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の情報や考察を発信していきますので、気になる方はぜひチェックしてくださると嬉しいです!
異世界転生ギャグわんこ漫画
ほくさいぬ
最新話は2025年9月12日 更新!


Amazonで無料配信中!
ミュージシャン・アーティスト・クリエーター向け
企画イベント・活動サポート
記事が見つかりませんでした。
本サイトでは、アフィリエイト広告を利用、またはプロモーション記事が含まれている場合があります